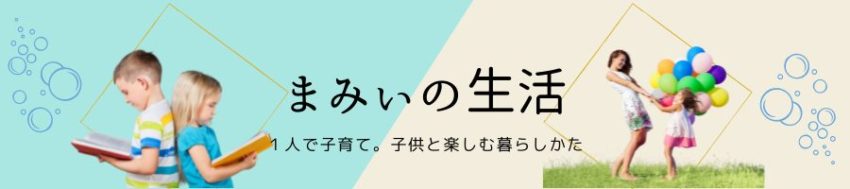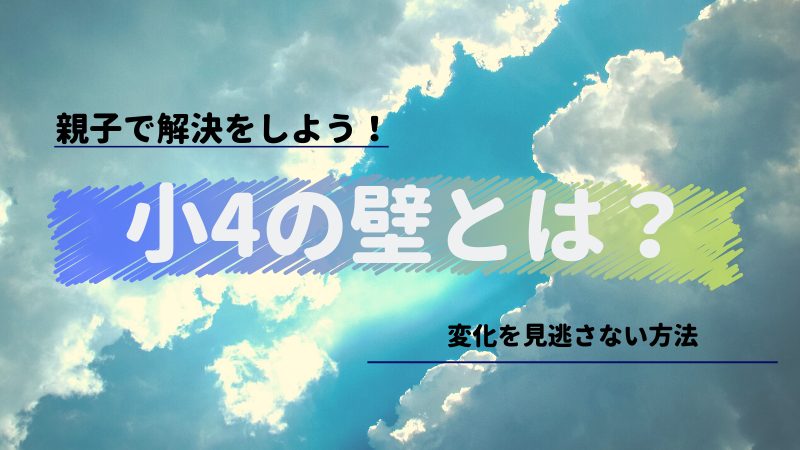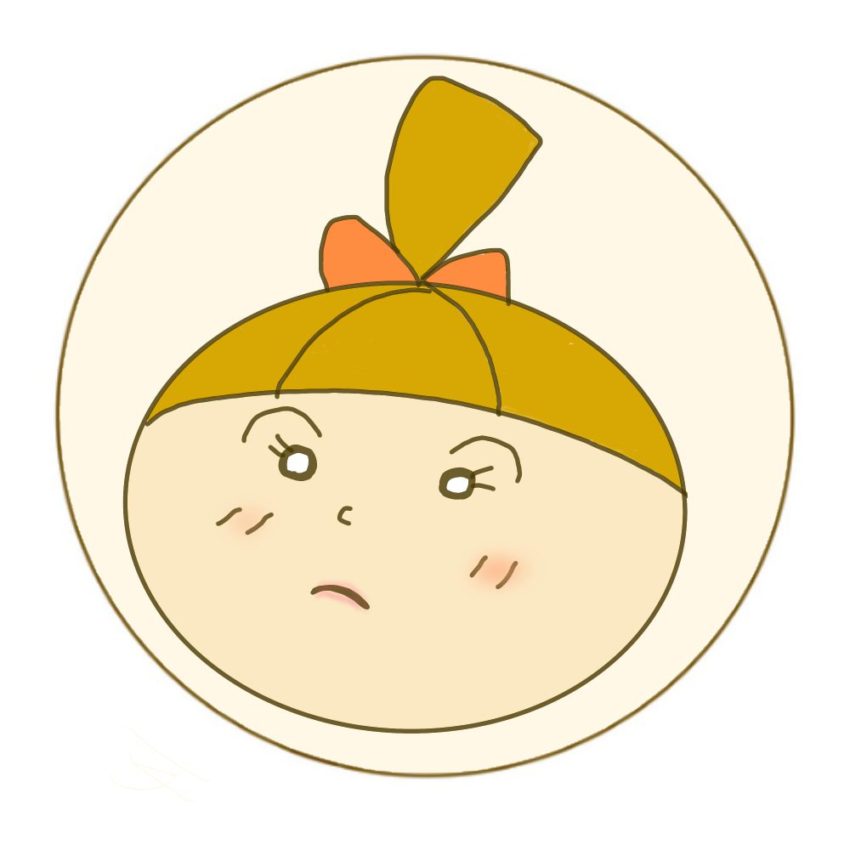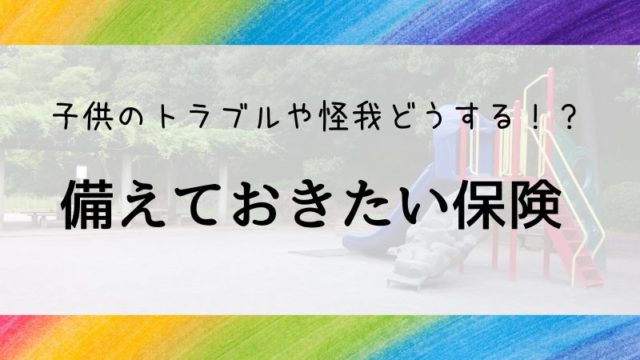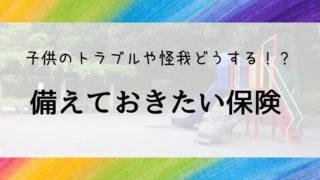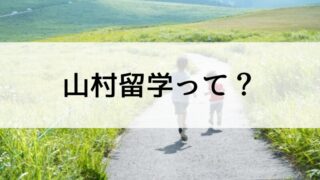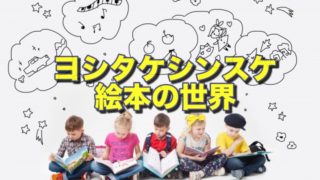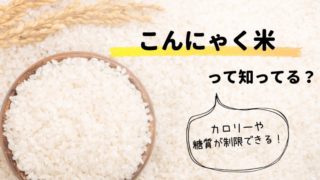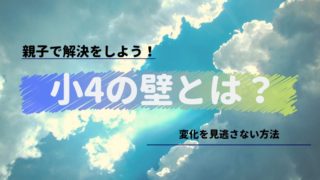ある日の夜、宿題をしていた小4の長男が私に突然言ってきた一言。
「ママ、ぼくクラスの友達がいないんだよね・・。」
そう言って息子の目がだんだんと赤くなっていく様子に、なんともいえない寂しさを覚え、胸のあたりがチクッとなりました。
今まで友達作りに何も興味を示していなかったのに突然どうしたんだろう?と思い尋ねると、『自分でもわからない・・。』との答えが返ってきました。
話をしていてもやけに否定的でネガティブな言葉を言うようになってきていることに気づいた私。
心配になり調べてみると、どうやら9歳・10歳の小学4年生ぐらいから子供はだんだんと『小4の壁』といわれる成長の変化がでてくる時期があるようです。
我が子もちょうどその時期にさしかかってきた様子。
今後のために詳しく調べてみることにしました。
『小4の壁』子供の様子が変わった?きっかけは学童保育や夏休みかも

そもそも小4の壁とは一体なに?
「小4の壁」は、小学校4年生前後(9歳〜10歳)の子ども達が脳の発達により、子どもから大人へと大きく成長する変化のことです。
この時期の成長過程で今までの変わりない普段の日常の中で疑問を持ったり、つまずきや自分と他人を比べ始め自信を失ってしまったりする感情を持つようになります。
たとえば、
- 言葉数が少なくなってきた
- だんだん反抗的になってきた
- 宿題の「わからない」が増えてきた
- 否定的な言葉を使うようになってきた
など、『あれっ?』と感じることが増えてくるかもしれません。
子どもの変化に早く気付き、少しでも力になってあげられたらいいですよね。
[小4の壁のきっかけ①]小3まで通っていた学童保育?
我が家の長男の変化のひとつは、学童をやめてしまったこともきっかけになったかもしれません。
小学1年生から3年生までお世話になっていた学童。
学校が終わると、そのまま学童に行きお迎えの時間まで友達と宿題や遊びを一緒にしたり、オヤツを食べたりして1日を過ごしていました。
4年生に進級後、学童を辞め学校から自宅へ帰ると一人で過ごす時間が増えた長男。
仕事から帰ると、宿題を広げながら動画をぼーっと観ているという状態が続いています。
『もう、一人でお留守番できるだろう・・。』と親の勝手な思いで辞めさせてしまったことを反省中です。
次男はまだ現在も学童に通っているため、同じ失敗をしないように次男が退所する際はきちんと話し合おうと思います。
[小4の壁のきっかけ②]長期休みや夏休み?
2021年の今年は特にコロナの流行で、外出やお友達とも遊ぶことができず夏休みを過ごすこの期間は子ども達も苦痛だったと思います。
どこのご家庭でもそうだったかもしれませんが、我が家の場合はゲームと動画漬けでした。
プールも図書館も開いていないので、どうすることも出来ず、母、怒ることも出来ない・・。こんな夏休みでした。
今年は通常とは違う臨時休校や長い夏休みがありましたが、普段でも長期間の休みは壁にぶつかる原因かもしれません。
理由として、
せっかく仲良くなったお友達が長期のお休みによって会えず遊部ことができない。
両親が仕事の為、一人で留守番をしながらの1日は暇すぎて過ごし方がわからない。
などがありました。
実際、長男は2学期が始まってから『クラスに友達がいない。』と言うようになりました。
4月から新学期が始まり、夏休みまでの約3ヶ月でやっと仲良くなり始めたお友達が長期のお休みによって、2学期が始まると少し距離ができてしまい自分から話しかけづらくなったようです。
『小4の壁』の原因は勉強や友達の悩みから始まることが多い

子どもの悩みのきっかけは家での生活の中だけではなく、学校の中でもでてきます。
小学4年生からは、算数や国語も基本を学ぶから考える応用へと変わってくる為、それに対応できなくなる子どもがでてきます。その中でも特に子供達を悩ませるきっかけが算数だそうです。
これまでの学習の積み重ねが不足していることで、「勉強が難しい」と感じたり、「わからないからやりたくない」と感じることが徐々に増えてきます。
確かに4年生の算数の教科書を見てみると、もう私も勉強が必要なくらい難しいです。
特に英語も必須科目になってしまい教えることすら出来ない状態です。
また、友達との付き合い方でも悩んできます。実際に我が家の長男の悩みのキッカケもこの『友達』でした。
その理由が学校で友だちと休み時間に校庭でドッジボールがしたいけど、「仲間に入れて!」の一言が言えずに結局ひとり教室で本を読んで過ごすということでした。
でも、この友達との付き合い方問題も『小4の壁』のひとつの特徴で、子どもが大人へと成長する「ギャングエイジ」ともよばれる時期でもあります。
9歳・10歳ごろから家族より友達と、友達との関係性に変化が出はじめ仲間意識が強くなり一緒に行動することが増えてきます。
この突然現れた『友達の悩み』は成長して行く上の1つの過程なんですね。
息子が通っている小学校では1年に1回希望者のみの相談期間があります。
相談する事で、先生も少し気にかけてくれるようになり私は相談してよかったなぁと思いました。
『小4の壁』の乗り越え方とその手段とは?

子どもが大人へと成長する過程においての変化はみんな経験することです。
大切なのはこの変化に早く築いてあげること。
だんだん変わってくる環境に私達親も戸惑いますが、子ども本人も心の変化にきっと惑っているはずです。
『あぁ。これが小4の壁なんだなぁ・・』と思い、どんと構えて成長を見守りましょう。
例えば勉強でつまづいている時には、つまづきのポイントを知り一緒に考えてあげたり、塾に行かせてみるなど。
親子のスキンシップも大事な事です!
私の場合は英語が苦手で教えてあげることができなかったので、小3から英語塾に行ってもらいました。
本人も英語というのが楽しいようで、お家でもちょいちょい単語を言っています。
今では、塾も楽しいようで行かせて良かったなぁと思っています。
また、一人で過ごす時間が多くなったことをキッカケに『お家で過ごすよりは・・。』と塾の利用を始めたご家庭もありました。
習い事や外出が多くなった子供達には、携帯やスマートウオッチなど見守り機能付きのものを持たせるご家庭も多いようです。
こちらも購入した際は、トラブルを避けるために使い方やルールをしっかり決めることが大切ですね。
我が家では長男に楽天モバイルを持たせてます。
まとめ
9歳から10歳にかけて、だんだん子どもから大人へと大きく成長していきます。
これを「小4の壁」と呼び、精神面の変化や反抗的な態度になったりしていくと思います。
我が家では長男が私に話してくれて変化に気付いたのですが、子どもの性格によっては何も話さない、親も気づかないという状態が出てくるかもしれません。
だんだん変わっていく子供の姿を感じるのは少し寂しい気持ちもありますが、大人になる第一歩のサポートをして見守ってあげてください。